現代マネジメント学科
経営管理論A
会社と社会の関係を知り、
自分自身が変革者に
なれる力を身に付ける。
経営管理を知ると、今まで見てきた風景が変わる
学生のみなさんは「経営管理」といわれてもピンとこないかもしれません。会社や経営を遠い存在と考える人も多いでしょう。しかし、経営管理は生活のさまざまな場面で自分自身に影響を及ぼす学問です。例えば、大学に入ってアルバイトをするとします。任される仕事が多くて「大変だ」と感じたとき、「仕方ない」と思ってあきらめますか? このとき経営管理を学んでいると、「こうしたらもっと良くなる」という視点を持つことができます。さらに踏み込み「バイトが忙しい組織的な原因は何か、改善するにはどうすればよいか」まで考えられるようになると、課題がより明確になります。自分が直面する状況に対する見方が180度変わる、それが経営管理という学問です。

会社の「内」と「外」が何かを知る
経営管理論Aでは会社の視点に立ち、主に会社と「外」とのかかわりについて考えます。一般に「外」にあたるものは取引銀行や市場、競合他社などで、逆に会社に属する個人(役員や従業員)が「内」となります。しかしどこまでが「内」でどこからが「外」という判断は意外に難しいもの。例えば店にとって客は外側にいる存在ですが、常連はどうでしょう。普通の客より店に与える影響が大きい常連は、内側により近い存在といえるのではないでしょうか。このように、視点の置き方によって「内」と「外」が変化します。これをどうわけるかは経営管理論の大きなテーマのひとつとなっています。
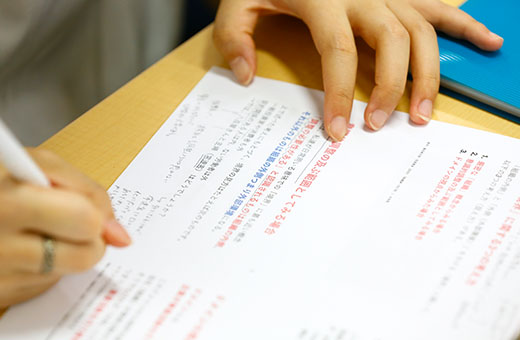
外部環境が会社に与える影響を事例から学ぶ
「外」には、国の方針や社会、文化、慣習などの外部環境も含まれます。これらが異なると、同じことをやっても異なった結果に行き着くことが少なくありません。ある会社が、日本で順調な売れ行きをみせる食品をイスラム教の国で販売しようとしました。しかし、宗教上禁忌とされる豚肉が使われているという話が広がり、大問題となります。調べると、原料に豚肉は使われていなかったものの、製造の過程で豚の酵素を使用していることが発覚。そのため商品は販売禁止となり、その後、製造方法を変更してようやく販売許可がおりました。これは宗教や習慣といった外部環境が会社経営に影響をおよぼした例です。ほかにもどのような外部環境が企業にどう影響を与えたか、さまざまな事例を知ることで経営管理の考え方を学んでいきます。
この授業は会社に属する個人、すなわち「内」について扱う経営管理論Bの授業へとつながります。AとBは独立した授業ですが、「内」と「外」の双方を知り、それが会社にどんな影響を及ぼすかを学ぶことで、自分の所属する組織を自分自身で変革するための考え方を身に付けることができます。


※この記事は、2019年度の授業内容を取材したものです。
