人間関係学科
ケースメソッドⅡ
福祉の現場で働く卒業生に
課題ややりがいを直撃。
専門知識を高めながら
自分に合う職場を見極める。
現場で働く卒業生3人が講師として登場
「障害者支援と人間関係」をテーマに、よりよい福祉現場のあり方や、支援方法を考えるケースメソッドⅡ。授業を受けるのは、社会福祉士をめざす3、4年生です。彼女たちはつい先日、別の授業(ソーシャルワーク実習)で1ヵ月間の現場実習を終えたばかり。これまでに経験してきた様々なボランティア活動と合わせ、現場で感じた気づきや課題を、1回の授業につき2~3人ずつ発表し、全員で議論していきます。一人の経験をみんなで共有することで、様々な事例に対応する力を養うことに加え、施設ごとに違う利用者や考え方、支援方法を知ることで、ソーシャルワーカーとしての引き出しや視野を広げるのが狙いです。
そして、今回は特別編。前回の授業で議論された、子どものいじめや虐待、貧困などについての現状を知るため、手嶋先生が卒業生を授業に招き、乳児院と児童養護施設で働く3人の先輩から、直接話を聞く機会をつくってくれました。

福祉現場の現状を知り、進路選択に活かす
授業では、まず先輩たちが勤務する事業所のパンフレットが配られ、事業概要に続き、各現場でのやりがいや課題が説明されます。乳児院では、乳児との意志疎通に苦労するのに対し、児童養護施設では、子どもから厳しい言葉を受けることもあるそうで、関わり方や環境に大きな差が。学生たちも、自分自身におきかえながら真剣に聞き入っています。さらに先輩たちは、入職1年目は思うような対応ができず自信を喪失した、2年目は周囲との人間関係に苦労した、3年目は自分のキャリアの重ね方に悩む、というように、年次ごとの課題ついても言及。就職後にぶつかる壁を予め学ぶことで、心構えや必要な準備を整えることができそうです。
その後の質問タイムでは、「面接試験の極意は?」「週末休めないのはどんな感じ?」など、先輩だからこそ聞ける本音が続々。「面接は自分の言葉で話したよ」「平日はどこも空いているから、かえって嬉しい」などの回答に、ホッとした様子の学生たち。あらゆる意味で現場のリアルを学べた授業となったようです。

現場の事例を学びながら、キャリア支援も
ひと通り質問が終わった授業の最後には、各自「振り返りシート」にその日の学びや気づきを記入します。今回は「乳児院と児童養護施設の両方を運営する法人に就職して、両方の現場を学びながらスキルアップする目標ができた」など、この授業が自身のキャリアデザインに役立ったという学生の声が目立ちました。
この授業は、振り返りシートと授業での発表の内容で総合的に評価されます。今回は「子ども」が対象でしたが、授業ではほかにも、「高齢者」や「障がい者」など、社会的に弱い立場にある人々への福祉を取り上げ、高齢者施設や障がい者施設、社会福祉協議会など、様々な福祉現場で働く卒業生を招き、生の声を聞く機会を設けています。就職する前に、「現場で働く人にしかわからない情報」が得られるこの授業。福祉の専門知識を高めるのはもちろん、キャリア形成にも大いに役立ちそうです。

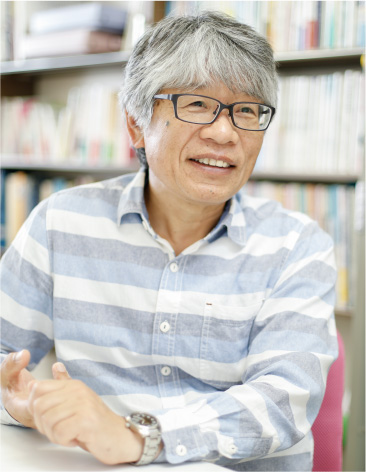
※この記事は、2018年度の授業内容を取材したものです。
