生活環境デザイン学科
インテリア実習II
人を幸せにする
空間をデザインする力と、
思いを伝える提案力を磨く。
全国的なデザインコンペに挑む
インテリアとは、室内のデザインだけではなく、人の営みを包み込む空間や環境全般を指します。すなわち屋外、自然の中にもインテリア的状況は存在しています。「インテリア実習Ⅱ」は、1・2年次でアパレルメディア、インテリア・プロダクト、建築・住居などを幅広く学んで培った基礎的な知識と技術を用いて、本格的なインテリアデザインに挑む授業。自分の専門性をインテリアデザイン分野に見出して選択履修した学生が、学びの集大成として作品に取り組みます。
この授業には、前半課題と後半課題があり、今日は後半課題で全国的なインテリアデザインコンペに向けたアイデアの中間発表です。学生はグループごとにコンペのテーマである「インテリアで創る幸せな空間」に沿ったアイデアを用意し、スケッチや模型、図面を手に、構想を説明します。加藤先生は「それは誰が使うの」「そこでの使い方や、形態は」「その社会的必要性は」WHO,WHAT,WHYの質問を次々に投げ掛けていきます。学生とのやり取りが始まります。

試行錯誤を繰り返してブラッシュアップする
「インテリア実習Ⅱ」は、能動的な姿勢で進める学習法であるアクティブラーニング形式を採用した対話型の体験授業です。学生はまず自らの着眼点、アイデアを発表していきます。それに対し加藤先生からデザインの対象者、提案の主体について、その主体と背景の関係や、社会的意義等の上記で説明したWHO,WHAT,WHYの順に質問が始まります。それを受けた学生が、質問に答えるといったやり取りを繰り返します。その間にそれらに関した様々な事例が口頭、スケッチ、ダイアグラム、図面等で解説され、学生の案をめぐって思考、対話、デザイン作業を深めていきます。デザインでは、多様な視点からの試行錯誤が重要となります。デザインコンペでは、伝えたい提案内容を限られた枚数のパネルにまとめて発表しなければなりません。完成度を上げるため、質問や講評、アドバイスといったやりとりが何度もなされ、学生たちの作品はその都度ブラッシュアップされていきます。
この学習過程には、グループワークを学ぶという意義もあります。「デザインは一人ではできません」と加藤先生が語るように、デザイナーはもちろん、どのような仕事であっても、依頼人、周囲の人とコミュニケーションを構築しながら「幸せな生活と空間性」を創成することが大切です。

良質なデザインをめざす意識を育む
加藤先生が、その熱い指導を通してめざしているのは、本当の意味で「良質なデザインを提案できる人」の育成。それは、人間の行為や身体、精神を深く観察してソフト部分である「コト」のコンセプトをしっかりと定めた上で、ハード部分の空間をつくり上げるというデザインプロセスを理解したデザイナーです。また前提としてデザイナーである前に魅力的な人間である必要があります。これができていないと、施主、スタッフから信頼されずコミュニケーションが成立せず、また良質さの追及も成立しません。いきなりプロ的な高度なレベルのデザインを望むのは順当ではありません。まずは、等身大の人間らしい感覚を大切にして、自らの思いやアイデアを大切にし、そこから思考、表現できるように導いていきます。
なお授業の前半では、「インテリアコーディネーター」の資格試験対策を行っています。資格取得の勉強も、後半のザインコンペに挑むことも、インテリアデザインを目指すうえで、基礎的な知識、設計力や、新たな生活や空間により「人を幸せに導くデザイン」提案力を在学中に体験・修得して、実社会に対応できる人材となるために必要な学びです。

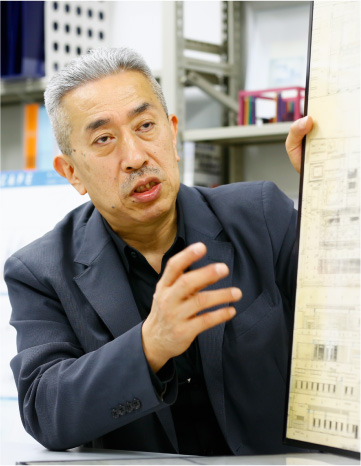
※この記事は、2018年度の授業内容を取材したものです。
