管理栄養学科
臨床医学概論
医療者と連携し、
患者さんの治療に栄養面で
貢献する管理栄養士を目指す。
病気と栄養の関係を、実例を通して具体的に学ぶ
管理栄養士は、チーム医療の一員となって患者さんの栄養ケアを担うことができる職業です。そのため、この授業では医療や介護の現場で必要な臨床医学の知識を修得します。消化に関連する臓器のしくみのほか、疾患の基礎知識、病気のメカニズムなどを取り上げますが、そこから栄養の問題を抽出し、管理栄養士として病気にどうかかわっていけるかを中心に学びます。例えば以前、給食中に子どもがアナフィラキシーショックを起こし、亡くなったことがありました。子どもの給食はアレルギーに配慮されたものだったのに、なぜこんなことが起こったか。それは、クラスメイトの残した給食をもらって食べてしまったからです。こういった事例では、学校現場を知らなければ原因にたどり着くことは困難です。しかし実例を知ることで、アレルギー→アナフィラキシーショックという図式がよく理解でき、病気を未然に防ぐための現場の重要性も認識できます。医学は決して簡単な学問ではないため、実例をまじえ具体的にイメージしながら授業を進めています。

管理栄養士には、専門知識のほかに提案力も必要
同じ病名でも病気の状態は人それぞれで、必要なケアも千差万別。病院で出された食事を「食べたくない」と拒否する患者さんも少なくありません。糖尿病食など制限のある食事は、どうしても美味しさでは劣るもの。患者さんに食事療法の大切さを理解してもらい、協力してもらうにはどうすればいいかを見極めるのも管理栄養士の仕事です。そしてよい案を見つけたら、今度は医師に提案し認められなければなりません。このように、管理栄養士には患者さんだけでなく医師を納得させられるだけの専門知識と提案力が要求されます。そのため大学では、医療人としての倫理や礼儀など管理栄養士として守り行うべき道を示した上で、基本的な医学の知識や専門知識、プレゼン能力、コミュニケーション能力も養っていきます。
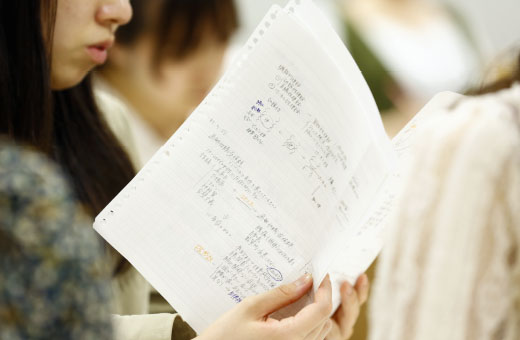
栄養のプロフェッショナルが担う未来
現在、特に高齢者介護の現場では、健康で豊かな老後を送るためには必要な栄養素を正しく摂取することが大切だという認識が広がっています。また、点滴や胃ろうで生命を維持するより、たとえ短くても好きなものを食べてのびのびと日々を送りたい、そう考える人も増えています。生き方は多様化し、食に関しても個々人が選択できる時代。そこでは一人ひとりと向き合い、最適な栄養ケアを提案・指導できる管理栄養士は必要不可欠な存在となります。大学で学んだ知識や技術を武器に、管理栄養士が活躍する道を拓いていってほしいと願っています。


※この記事は、2019年度の授業内容を取材したものです。
