表現文化学科
小説創作(習作)
芸術は人生を助け、
心を豊かにしてくれる。
そんな「絵空事」を自分自身で創り出す。
書くのは一人ひとりでも、授業はみんなでつくる
小説創作の授業には、ここで紹介する「習作」と、さらに進めて作品全体を考える「発展」があります。習作では物語を構成する「パーツ」、例えば世界観の構築やキャラクターのつくり方、人間関係の考え方、セリフの書き方などを学び、実際に文章を書いていきます。クラスにはすでに作家を志して創作活動を行っている学生から、今まであまり文章を書いてこなかった学生まで、タイプもレベルもさまざま。そんな多様な学生たち全員が課題をもとに作品を書き、発表し、感想を述べ合います。その内容に説明を加えながら授業を進めるので、学生の作品すべてが教材。それだけに、出された課題に対して気を抜かず、丁寧に文章を仕上げること、そしてクラスメイトが書いた作品に敬意を持ち、批判精神をもって吟味することの大切さを、まず最初に伝えます。

人物相関図・日記・昔話など、さまざまな課題から創作を学ぶ
授業ではさまざまな課題を用意しますが、自分が書きたい小説の人物相関図をつくるというのもそのひとつ。主人公を中心に、片思い相手・友人・隣の住人など設定を考え、人物間で湧き起こる感情や行動を想像します。グループで検討するとよりイメージがふくらむので、出された意見を参考に個々人が小説を書き進めていきます。その他には他人になりきって日記を書く、昔話を主役以外の視点で物語る、などの課題があります。これは創作に慣れていない学生でも書きやすいため、面白いアイデアが次々に飛び出してきますよ。ただし創作では、他の作家が生み出した世界観を使うことはNG、そして超能力を使う内容は要相談としています。自分で世界を創り、一つひとつのピースを組み立てストーリーに仕立て上げることが大切なのに、超能力はそれだけですべてが解決してしまいますからね。
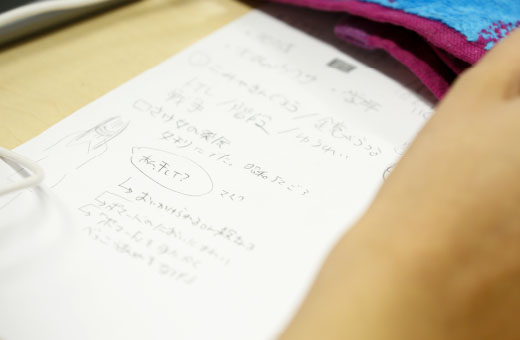
「読ませる」ための文章力と構成力は、創作以外でも生きる
学生同士で作品を読み合うことは、文章に対する苦手意識の克服に非常に有効です。「隣に上手な文章を書く人がいる」とわかれば刺激になりますし、自分に高いレベルを求めすぎている人は肩の荷を降ろすことができます。読みづらい文章は、声に出して読むことでどこに問題があるか気づきます。教員が添削するより効果的ですね。物語はあらゆる可能性を内包し、作者は世界を自由に操ることができるので、授業を通して一番に身に付くのは想像力だと思います。そしてそれを表現する文章力と構成力。授業を経験した学生は、自分を押し付けるだけでなく、少し引いてアピールするような読ませ方の演出ができるようになるため、就職活動のエントリーシートも上手に書く人が多いです。最初は「書き方がわからない」と言っていた学生も、最後には自分で書き進められるようになりますよ。


※この記事は、2019年度の授業内容を取材したものです。
