国際言語コミュニケーション学科
Introduction to Linguistics
All Englishで
言語について考え
Linguisticsの
多彩な魅力に触れる。
毎週一分野ずつ開かれていく言語学の世界
Linguisticsとは、言語学のことです。『Introduction to Linguistics』は、高校まで触れることのなかった言語学の世界へとやさしくいざなう、学習の導入とも言える授業。2年次から4年次までの学生を対象に、前期に開講されています。授業では毎回、Phonetics(音声学)、Semantics(意味論)など言語学の一分野を取りあげて紹介しながら、学術的な定義や理解の進め方について考えていきます。すべて英語で進められるAll Englishの科目です。
いつもように前回のおさらいの後、担当教員のDiCello先生が用意したプリントの哲学的な質問事項に答えることから授業はスタートします。たとえば、「People are the only animals that have language」という質問。Agree/disagreeで回答し、なぜそう考えるかを英語でディスカッションするうちに、分野ごとの学びの概念や何を考える研究なのかという理解の入口へと導かれていきます。

身近な例を題材に、英語を使って理解を深める
今回学ぶ言語学は、Semantics。日本語では意味論と訳されます。辞書やインターネットでこの意味論という言葉を調べても学びの内容をつかめないように、言語学の多くの分野はひとことでは説明することができません。DiCello先生は、イラストや写真を添えたプリントとスライドを使い、できる限り身近で簡単な例を挙げて説明していきます。
たとえば、今日配布されたプリントに記されたドクロマーク。何の印だと考えるでしょうか。基本的には世界共通で「毒劇物」を表すサインとされています。しかし、授業では「海賊」と捉える学生が多いことがわかりました。このように、本物の物質と言葉がどのようにつながっているかを考えることはSemanticsの一部。母語が異なる人同士の共通理解についても追究できる学問です。ツアーコンダクターなど外国語によるコミュニケーションを必要とする仕事や、誰が見てもわかるようにデザインするピクトグラム、Webサイトの作成にも役立ちます。
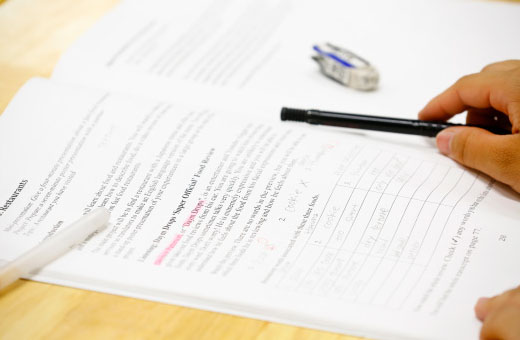
次は、専門的な学びを進めるステージへ
DiCello先生は、「たとえば、Pragmatics(語用論)を突き詰めて学びたい場合は木村隆先生の『応用言語学』の授業がありますよ」と、分野ごとに専門の先生やゼミを紹介するようにしています。国際言語コミュニケーション学科のカリキュラムには、言語学に関する科目やゼミが豊富に用意されているからです。なお、『Introduction to Linguistics』に直接つながるのは、併せて受講が義務づけされている後期の『Linguistics』です。
英語の中学校・高等学校教諭一種免許状取得のための必修科目でもある『Introduction to Linguistics』は、英語教師をめざす学生にとって、言語習得の過程を見つめ、より良い教え方を考える絶好の機会。英語学習者としても、自分のつまずきの原因を客観的に分析する目を磨くことに役立ちます。自分の意見を英語で表現することを通して、第一言語である日本語の使い方や学び方と比較し、違いを説明できる力が身につけられる授業です。


※この記事は、2018年度の授業内容を取材したものです。
