表現文化学科
ポップカルチャー概論
身近なメディア作品の
本質を見つめ、
社会や時代を
より深く理解する。
文学のようにポップカルチャーを読み解く授業
「ポップカルチャー概論」は、第二次世界大戦以降にロックンロールの登場などによって新しく生まれ変わった、現代の「大衆文化(ポピュラーカルチャー)」をポップカルチャーとして捉え、考える授業です。その発生と発展、流行の背景にある時代や社会、文化、思想など、ポップカルチャーの本質を理論的に分析し、評価する技法の習得をめざします。
担当教員の長澤唯史先生は、小学校時代からの洋楽好きが高じてアメリカ文学研究への道を歩み出したという経歴の持ち主。研究者人生の入り口となったポップカルチャーをこよなく愛し、文学のあ一部として研究を続ける長澤先生が、誰もが知っているメディア作品を読み解く授業は魅力たっぷり。知っているつもりだった身近なエンターテイメントが、今までとは全く異なる輝きを放って見えてきます。これまで自分が考えてもみなかった解釈を通して、ポップカルチャーへの興味が生まれ、新たな世界への視野が開かれる授業です。

「なぜ面白いのか」を追究すると、自分自身が見えてくる
本日の授業の題材は、K-POPとJ-POP。「そもそもK-POPって何だろう?」「K-POPという言葉は誰が最初に使いはじめたんだろう?」などの問いを立てながら、韓国のポップミュージックの背景を紐解いていく長澤先生。アメリカのヒットチャートを賑わせるK-POPの快進撃に対して、なぜJ-POPは世界に受け入れられないのか。もともとは韓国に影響を与えていたはずの日本の音楽や映画が90年代以降に大きく遅れをとったのはなぜなのか。授業を通して見えてきたのは、K-POPの誕生には歴史や政治、日韓関係が大きく関わっているという事実と、韓国の姿、そして日本の姿でした。
「このように、ポップカルチャーを追究すると、必ず自分に戻ってきます」と、長澤先生は語りかけます。社会が今なぜその作品を求めたのか、なぜ興味を掻き立てられるのかを考えれば、おのずと自分自身が見えてくる。それが、この授業のゴールでもあるのです。

興味と理解をさらに深める道筋を用意
あらゆるポップカルチャーには、民族の歴史や文化が深く関わっています。たとえば、なぜアメリカでは黒人音楽の人気が高いのかを考える際には、人種問題に関する理解が欠かせません。このような関連する知識の習得を支えるのが、古典から現代に至る世界の多様な文化の理解をめざした表現文化学科の授業群です。「ポップカルチャー概論」が属するのはポップ・カルチャー・スタディーズ科目群ですが、たとえばモダン・スタディーズ科目群には、「アメリカ社会の諸問題」「アメリカの人種民族問題」の授業があり、学びを深める手立てとなります。
また、映画や音楽など、あらゆるメディアの作品分析や、小説をドラマや映画用に改作・脚色するアダプテーションなどにも、「ポップカルチャー概論」で培った、作品を読み解く力は必ず役立ちます。自分を見つめ、社会を見つめることで、自分自身の得意分野や今後やりたいことを見つけるきっかけにもなる授業です。

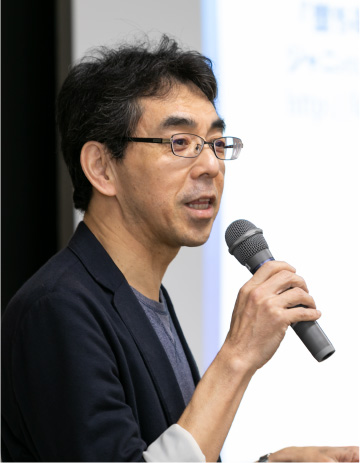
※この記事は、2018年度の授業内容を取材したものです。
